【社労士試験】2月末までの短期目標【独学合格体験記7】
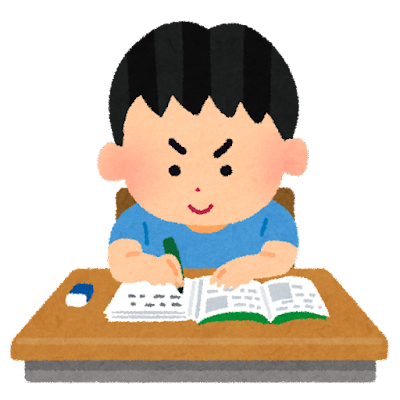
●2月末までの短期目標を立てる。
前回の記事【勉強日記⑥】で、2023年が明けてから年度末までは「理解(テキスト読込)」ではなく「暗記」を行うと書いた。
しかし、「暗記」作業にどの程度の時間を要するのか判然としなかったので、具体的な短期目標を立てられずにいた。
【勉強日記③】にも書いたように、「欲望への服従度」は「長期的欲求」よりも「短期的欲求」の方が高いのだから、「短期目標」を設定しないのは都合が悪い。実際、1月の勉強は漠然とした曖昧なものに終始してしまった。
早急に短期目標を設定し、軌道修正を図らねばならない。
年初時点では、「問題集」と「あんちょこ本」のボリューム等も把握していなかったため、短期目標のケツ(締切)すら定められないでいた。
1ヶ月間それらを使用してみて、だいたいの予測を付けられるようになった。
以上から、当面の短期目標を次のとおりとする。
下記2点を、2月末日までに行う。
①「問題集」2冊のうち、「択一式」用を全科目最低1周する。
②「あんちょこ本」を全科目最低3周する。
●①「問題集」の消化について。
本試験は、「選択式」と「択一式」の2種類が行われる。問題集もそれに合わせて、「選択式」用・「択一式」用をそれぞれ1冊ずつ購入した。
しかし、ボリュームから考えて、2月末までに2冊ともを終えるのは難しそうだ。
どちらかに絞る必要がある。
先に消化すべきなのは、明らかに「択一式」の方だ。
本試験において「理解」をより求められるのは、「択一式」だ。用語や数値をダイレクトに問うてくる「選択式」に比べて、単純な「暗記」だけでは解けない問題が相対的に多い。
社労士試験は記述式ではないのだから結局のところ「暗記」が勝負を決するが、とは言え、「理解」できるものはしとくにこしたことはない。
「択一式」の問題ならば、「暗記」の確認だけでなく、「理解」の確認もできる。
本試験までは時間的余裕もあるので、「暗記」と「理解」を同時並行的に進められる「択一式」の問題集を先に消化すべきだ。
●②「あんちょこ本」の消化について。
まえがきに書籍の目的が記載されていたが、その内容が僕が【勉強日記⑥】で意図していたこととまったく同じだった。
すなわち、「横断整理に力点を置いた暗記本」ということだ。
社労士試験で必要とされる内容は広範に及ぶ。しかし、忘れてはならないのは各分野を比較したときに、重複している部分もそこそこ多いということだ。
重複している点は「アレと同じ」とだけ覚えておけばいい。
購入した「あんちょこ本」も重複部分はバッサリとカットされている。テキストのように重複する内容をわざわざ記載してはいない。
一方、他の分野と明らかに異なっている点は、個別に暗記をすればいい。そして、その作業は基本的にテキストでも足りる。
暗記をするうえで圧倒的に問題なのは、「他の分野と同じと見せかけて、微妙に違う」点だ。
これが社労士試験でもっとも鬱陶しいところだ。
こんがらがるのである。
こっちではこれはこっち、あっちではあれはあっち、こっちではあれはこっち、あっちではこれはあっち……。
テキストは記載箇所がもちろんそれぞれの分野に分かれているので、「分野ごとの比較」が難しい。
それを「あんちょこ本」は解決してくれる。
自分で「科目横断的な内容比較」をまとめてもいいかもしれないが、途方もない時間を要することは目に見えている。
科目横断的な「あんちょこ本」は、社労士試験の勉強には必須と言えるだろう。
●今後の基本戦略。
今後の基本戦略は、「『あんちょこ本』での暗記 ⇔ 『問題集』での確認」の反復作業となる。
ときどき、「テキスト」を開くかもしれない。
しかしそれは、問題集で真正面から「理解」を問われる難問に出会ったときや、「選択式」対策の「個別具体的な用語(術語)」の確認のためだ。
社労士試験の勉強の柱となる「暗記」は基本的に「あんちょこ本」で行う。混乱を避けるためにも、絶対にその方がよい。
以上。
結果報告は3月上旬に行う予定。


